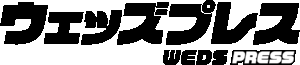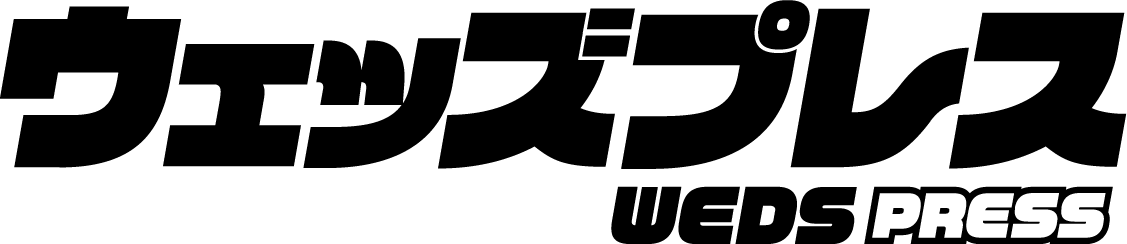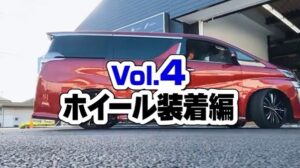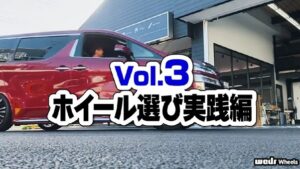初心者のための「ホイール選びの基礎」を4回にわたってお届けするこのシリーズ。
前回(第1回)は、TGR TEAM WedsSport BANDOH 坂東正敬 監督とレースアナウンサー勝又智也 氏が、ホイールのサイズ選びや製造方法について詳しく解説した。
インチやリム幅、インセット、そして鍛造やフローフォーミングなどの製法が、見た目と走りにどう影響するのか、いざ聞かれると説明するのが難しい……という人も多かったのではないだろうか。
第2回となる今回は、ホイールの安全性を裏付ける「規格」と「保証」に焦点を当て、ちょっと難解な内容を分かりやすく+楽しく+おかしく解説。
近年増えている模造品や中古品を使用することのリスク、そして正規品が持つ“信頼の証”を理解することで、より安全で安心なホイール選びが可能となるはずだ。

目次
模造品に潜む危険と正規品の価値
近年、ホイール市場では模造品やコピー品の流通が問題となっている。見た目は本物そっくりで、価格は正規品の半分以下という例もあるが、使用素材や製造工程の品質が大きく劣る場合が多い。
鋳造工程での管理が不十分であれば、内部に気泡や不均一な金属組織が生じ、強度は著しく低下する。
坂東監督は、「海外でコピー品のスニーカーを購入したら、歩いて数歩でソールが剥がれた」と自身の経験を例に挙げ、「外見の類似は安全性の保証ではない」と強調する。

スニーカーとは異なり、ホイールが走行中に破損すると制御不能や横転事故に直結するため、命の危険を伴う。価格の安さに惑わされず、正規品の価値を理解することが不可欠なのだ。
JWLとVIA――安全を裏付ける二大規格
レースアナウンサー勝又氏が「ホイールの規格、何種類あるか知っていますか?」と質問すると、坂東監督は「wedsの規格の数? 商品企画の人数しか知らない!」というコントのようなやりとりも。


今回は、前回登場した“天の声”ことwedsの商品本部・中村氏が、品質基準の詳細などについて解説をしてくれた。


JWL(Japan Light Alloy Wheel)は、日本国内で販売される軽合金製ホイールに義務付けられた強度試験規格。メーカーが自らの責任で行い、試験条件は走行環境を想定した厳格な基準が設けられている。
径や幅の異なるすべてのサイズに対して試験を行う必要があり、同一デザインでもバリエーションごとに検証を繰り返す必要があるとのこと。

VIA(Vehicle Inspection Association)は第三者機関が実施する試験で、JWLと同等の内容を外部機関の立場で確認するものだ。
このVIAマークは「外部の専門機関が保証した安全性」の証であり、認証品としてVIA登録された商品にのみ使用が許されている。
自社オリジナルホイールをVIA登録するには、業界団体JAWA(日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会)への加盟が必須。
JAWAへの加盟と自社商品がVIAに登録済か否かが、メーカーの信頼度を示すという。



3つの強度試験で確かめる安全性
規格試験は回転曲げ疲労試験、ドラム試験、衝撃試験の3つで構成される。
回転曲げ疲労試験は、コーナリングなどでの耐久性を検証するための試験で、ホイールに横方向の負荷をかけた状態で規定数を回転させてその損傷などをチェックするもの。これは金属疲労による亀裂発生を防ぐための重要な指標となる。
ドラム試験は、主にホイールの縦方向や直進状態での上下運動での耐久性を検証する試験。タイヤを装着した状態で負荷をかけて規定数回転させ、損傷状態をチェックする。高速道路や長距離輸送など過酷な条件を想定した試験である。
衝撃試験は、縁石に乗り上げた際の衝撃や路上の障害物との接触を再現するため、ホイール上部からおもりを落下させてホイールの損傷状態をチェックするもの。ホイールの損傷状態はもちろん、それに伴う急激な空気漏れが発生しないかを確認する。
デザインと強度のせめぎ合い
ホイール設計では、軽量化とデザイン性、そして強度の確保が常にせめぎ合う。細身のスポークや肉抜き加工は軽量化と美観の向上につながるが、その分局部的な応力集中が起きやすくなる。
「ホイールメーカーさんでいろいろなデザインをしないといけない中で、強度も考えながらデザインしなきゃいけないっていうのは、結構大変ですよね」と勝又氏。

近年は大径ホイールが主流となり、デザイン上スポークが長く細くなる傾向がある。これに対応するため、メーカーはCAE(Computer Aided Engineering)による解析や試作試験を重ね、強度不足が予測されれば設計変更を行っていくという。
型の作り直しには膨大なコストと時間がかかるが、wedsは安全性を犠牲にする妥協はしない。こうした背景が、信頼できる製品を支えているのだ。
保証とPL保険がもたらす安心
「ホイールを購入するときに一番気をつけていただきたいのは、必ず保証書を持っていること。最近、ホイールもインターネットで簡単に買えますけど、なければもらってください」(勝又氏)。
保証書は基本的に再発行できないため、注意が必要だ。

wedsの正規品には必ず保証書が付属し、通常使用での変形や塗装剥がれなど、一定期間内の不具合に対応する。購入時には販売店の押印が必要で、紛失や未押印では保証が受けられない。
また、ホイールに貼付される品質認定ホログラムシールは「PL保険(製造物責任保険)」の証明となる。
「PL……桑田・清原?」(坂東監督)
「古い(笑)」(勝又氏)


PL保険は製品の欠陥が原因で損害が発生した場合に補償を行う制度であり、消費者は製品の安全性とメーカーの責任体制を確認できる。

ホイールは単なる外装パーツではなく、車の走行性能と安全性を支える重要部品である。JWLやVIAなどの規格試験、業界団体の加盟、保証書やホログラムシールといった「安全の証」を確認することが、事故やトラブルを防ぐ第一歩となる。
ただし近年はwedsのように人気が高いホイールのニセモノがインターネット上で保証書なしで出回っていたり、中古や個人売買でも保証や保険が適用されない場合も多い。
そのため、購入前には品物の真偽や保証書の有無の確認が必須なのだ。
今回の動画でも、坂東監督・勝又氏は口をそろえて「新品かつ正規品を信頼できる販売店から購入することが、長く安全に愛車を楽しむための最も確実な方法」と話していた。
次回は実車で「ホイール選び実践編」!
次回はスタジオを飛び出して、実際の車を使ったホイール選びのポイントを実演する。
スペシャルゲストも登場し、実物を前にしたサイズ感やデザインの見え方、走行時の印象の違いなどをリアルに紹介。
第1回・第2回で得た知識を総動員した、「愛車にベストな一本」を選ぶための実践編なので、お見逃しなく。

「初めてホイールを変えたい人」必見!
今回の記事の動画は、YouTubeチャンネル「wedschannelーウェッズチャンネルー」で公開中!
■失敗しない ホイールの選び方
▼Vol.1[座学編]
▼Vol.2 [規格・保証編]
▼Vol.3 [ホイール選び実践編]
▼Vol.4 [ホイール装着編]
weds緊急アラート!! 偽物アルミホイールがアブない!!!