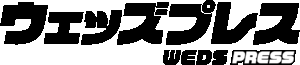
Category
Tags
BRZ GR86 SUPER GT SUV WEDS ADVENTURE WedsSport WedsSport Racing Gals アルファード ジムニー ジムニーノマド スポーツカー スーパー耐久 ホイールの知識, ホイールの選び方 ミニバン モータースポーツ ヴェルファイア 富士スピードウェイ 浅野レーシングサービス

ホイール選びは見た目の印象だけでなく、サイズや構造、製造方法など多くの要素を理解することが欠かせない。
デザインやカラーの好みだけで決めてしまうと、思わぬ失敗や安全性の問題につながることもあるからだ。
そこで今回から始まった「初めての失敗しないホイールの選び方」シリーズでは、TGR TEAM WedsSport BANDOH 坂東正敬 監督とレースアナウンサー勝又智也 氏が、初心者のための「ホイール選びの基礎」を4回にわたって解説。
また時には、天の声としてwedsの商品本部・中村氏も登場する。
専門用語の意味を説明しながら実際の選び方や注意点を掘り下げて、失敗しないためのポイントを“わかりやすく+楽しく+おかしく”お伝えしていくので、ご期待あれ。
今回のゲスト、SUPER GTで活躍する坂東正敬 監督と、レースアナウンサーの勝又智也氏がまず強調したのは、「街のタイヤ・ホイールショップやカーイベントを訪れて現物を確認し、スタッフと話すこと」の重要性だ。
ネット検索で多くの情報が手に入る時代だが、最終的な確認や判断はメーカーやショップで行うのが安心。ネットで知識を得たうえで、最後の最後にメーカーに相談する……という人も少なくないという。
イベント会場やショップでは、同じ車種や似た雰囲気の車を見つけて、その装着ホイールのサイズやデザインを参考にすることができる。
SNSで見かけたかっこいい車のホイールを真似するのも一つの手だが、実際に自分の車に合うかどうかは、現場で確かめるのが確実である。
wedsの販売協力店へ直接問い合わせることで、精度の高いアドバイスが得られるはずだ。
ホイールは、車全体の印象を左右する「足元のファッション」。監督はホイールを「クルマのスニーカー」にたとえていた。
スニーカーのデザインや色が履く人の個性を表すように、ホイールもオーナーのセンスや好みを映し出すためである。
車体カラーとの組み合わせは、印象作りの大きな要素。黒い車に赤いホイールを合わせてスポーティーに見せたり、白い車に黒いホイールを合わせて引き締まった印象を出したりと、配色次第で車のキャラクターは大きく変わる。
場合によっては、黒い車に黒いホイールを合わせて、あえて渋くまとめる選択もあり。
また、ホイールの構造にも注目したいところ。1ピースは軽量で剛性が高く、スポーツ走行に向く一方、2ピースや3ピースはデザインやサイズの自由度が高く、高級感を演出できるという。
例えば、アルファードのような大型ミニバンには2ピースや3ピースがよく似合うし、GR86のようなスポーツカーには1ピースのスポーティーなモデルが映える。
ホイール選びに欠かせないのが、サイズに関する知識である。まず「インチ」はホイールの直径を示し、純正が18インチの場合、19インチに変更することを「インチアップ」と呼ぶ。
見た目の迫力を増すためにインチアップする人は多いが、その際にはリム幅とインセットの選択も同時に考える必要がある。
リム幅はホイールの横幅を示し、単位はインチとなる。1インチは2.54センチメートルに相当する。「J」は幅の単位ではなく、リム外縁部分の形状を表す記号のこと。
たとえば「9J」という表記は、幅が9インチでJ形状のフランジを持つホイールを意味する。
インセット(またはオフセット)は、ホイールの取り付け面がリムの中心からどれだけずれているかを示す数値だ。
プラスの値で内側寄り、マイナスの値で外側寄りにホイールが装着される。
この数値次第で、フェンダーとの位置関係や車検適合性が変わるため、見た目と安全性の両立を意識する必要がある。
サイズの選び方には正解が一つではなく、車種ごとに適した範囲がある。基本となるのは純正サイズで、そこから車高やフェンダー形状を踏まえて、どこまでインチアップやリム幅拡大が可能かを判断する。
wedsの公式サイトには、車種別の推奨サイズ表が掲載されており、ブランドごとにターゲット車種やオフセット設定が決まっている。これらの情報を参考にすることで、自分の車に合うホイールを効率よく絞り込むことができる。
ブランドによって狙うターゲットが異なり、軽自動車向けと大型車向けでは当然、仕様が異なる。
ホイールの製造方法は、大きく分けて鍛造(たんぞう)、鋳造(ちゅうぞう)の大きく2種類がある。
鍛造は、高圧で金属を押し固めて成形する方法。金属内部の密度が高くなるため軽量で強度が高く、モータースポーツなど高い性能が求められる場面で重宝される。
鋳造は、溶かした金属を型に流し込んで成形する方法で、自由度が高くコストを抑えやすいのが特徴。
フローフォーミングは、鋳造や鍛造で作ったリム部分を回転させながらローラーで伸ばす製法のこと。ろくろのように回転させながら成形するため、リム部分を薄く軽く作ることができ、強度も十分に確保できる。
現在では1ピースホイールを中心に広く採用されており、軽量化と強度のバランスに優れた方法として注目されている。
ホイールは見た目や性能だけでなく、安全性を担保する規格にも注目する必要がある。規格は言わば「ホイールの生命保険」のようなもので、これを満たしているかどうかが安全性の基準になる。
新品を正規ルートで購入した場合、メーカー保証が付くことも多く、万が一の不具合時には交換や修理の対応が受けられる。逆に並行輸入品や中古品では保証が受けられない場合があるため、注意が必要とのこと。
ホイール選びは単なる見た目の問題ではなく、車種や使用目的に応じたサイズ、カラー、構造、製造方法、そして安全性や保証までを含めて総合的に判断することが大切。現物を見て確かめ、専門家に相談しながら選ぶことで、満足度の高い選択ができる。
車は足元を変えるだけでガラリと印象が変わるもの。だからこそ、ホイール選びは慎重に、しかし楽しみながら行うことが、愛車との付き合いをより豊かにしてくれるだろう。
今回の記事の動画は、YouTubeチャンネル「wedschannelーウェッズチャンネルー」で公開中!
■失敗しない ホイールの選び方
▼Vol.1[座学編]
▼Vol.2 [規格・保証編]
▼Vol.3 [ホイール選び実践編]
▼Vol.4 [ホイール装着編]